blog
住宅購入を『資産』として考える

住宅購入は多くの人にとって人生で最も大きな買い物のひとつです。
そのため「住まい」としての快適さやデザイン性に目を向けがちですが、同時に「資産」としての側面を意識することが欠かせません。特に20代~30代の世代にとって、住宅は長期的に所有する可能性が高く、将来の資産形成やライフプランに大きな影響を及ぼします。
最後まで読めば、住宅購入のポイントがわかりますので、ぜひご覧ください!
住宅購入を「資産」として考える重要性
住宅を「資産」と捉える最大の理由は、土地や建物が将来にわたり一定の価値を保ち、売却や賃貸という形で資金化できる可能性があるからです。近年は「持ち家=負債」という考え方も広まっていますが、立地条件や建物の管理次第で住宅は確かな資産となり得ます。逆にこれらを軽視すれば、価値が大きく下落し、経済的な負担を背負うリスクもあるのです。
また、住宅はローン返済を通じて「強制的な貯蓄」となる点も見逃せません。長期にわたり支払いを続けることで、最終的には土地や建物という形の資産が手元に残ります。特に若いうちに購入すればローン完済の時期が早まり、老後の生活基盤を安定させる効果も期待できます。
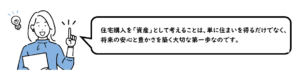
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
資産価値を左右する要素とは

2-1. 土地の価値とエリア選び
住宅の資産価値を大きく左右する最大の要因は「土地」です。建物は経年によって劣化し価値が下がっていきますが、土地は時間が経過しても価値がゼロになることはなく、むしろエリアの発展によって上昇する可能性を秘めています。特に駅近や主要道路へのアクセスが良い場所、商業施設や教育環境が整った地域は需要が安定しやすく、将来の売却時にも有利に働きます。
一方で、利便性の低いエリアや人口減少が進む地域では、購入価格が安くても将来の資産価値が下落するリスクが高いです。そのため住宅購入を検討する際は、現在の住みやすさだけでなく、将来の人口動向や都市計画を調べることが重要です。20代~30代の若い世代が長期的な視点で土地を選ぶことは、将来の資産形成に直結します。
2-2. 建物の価値と経年劣化
建物は新築時に最も価値が高く、築年数を重ねるごとに徐々に下落していきます。特に木造住宅の場合、築20~30年で市場価値が大幅に下がるケースも珍しくありません。ただし、必ずしも「古い=価値がない」わけではなく、適切なメンテナンスが行われているか、耐震性や断熱性など性能面が時代に合っているかによって評価は変わります。
また、最近では中古住宅を購入してリノベーションするスタイルが広がっており、建物の質やリフォームの可能性によっては長期的な価値維持が可能です。
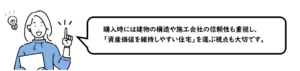
2-3. 住宅ローンと資産形成の関係
住宅購入において多くの人が利用する住宅ローンは、資産価値を考えるうえで無視できない要素です。ローンの返済額が家計を圧迫しすぎると、せっかくの資産が「負債」となりかねません。逆に、無理のない返済計画を立てれば、長期にわたる支払いが「資産形成のプロセス」となります。
特に低金利の時期に借り入れを行えば、将来的にインフレや不動産価格の上昇があっても、固定された返済額によって実質的な負担は軽減されます。20代~30代で住宅ローンを組むことは長期的に見ればメリットが大きく、完済後には土地や建物が「純粋な資産」として残るため、将来の安定につながります。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
20代~30代で住宅購入を検討するメリット

3-1. 早期購入による将来の資産安定
20代~30代という若い世代で住宅を購入する最大のメリットは「時間を味方にできる」ことです。住宅ローンは一般的に35年という長期で組まれることが多く、40代以降の購入では完済時期が定年後にずれ込みやすくなります。若いうちに購入しておけば、60歳前後でローンを完済でき、老後に住宅費の負担がなくなります。これは将来の資産形成において大きな安心材料となります。
さらに、早期に住宅を所有することで、建物や土地が長期間にわたり資産として蓄積されます。万が一ライフスタイルが変化しても、売却や賃貸に活用できる選択肢が残り、柔軟な資産戦略を描くことが可能です。
3-2. 賃貸と購入の資産価値比較
若い世代では「賃貸か購入か」で迷う方が多いですが、資産という観点で比較すると大きな違いが見えてきます。賃貸住宅に支払った家賃は、将来的に何も残らない「消費」として扱われます。一方、住宅を購入すればローン返済がそのまま「資産の積み立て」に変わり、最終的に土地や建物という形で自分の資産として残ります。
もちろん、賃貸には転居しやすい、維持管理の責任が少ないという利点もありますが、長期的に見ると資産を築く効果は限定的です。
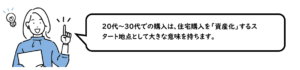
3-3. 若年層だからこそ活かせるローン活用
住宅ローンは借入期間が長いほど毎月の返済負担が軽減されやすいため、若いうちに組むことは有利に働きます。また、金融機関は安定した職歴や将来性を考慮して審査を行うため、20代~30代の若い世代は比較的柔軟に条件を選びやすいという特徴もあります。
さらに、最近では「変動金利」や「固定金利」など選択肢が豊富にあり、ライフプランに応じた組み合わせが可能です。早期に住宅ローンを利用し始めれば、長期間にわたり資産を増やすサイクルを形成でき、将来的に住み替えや投資用不動産としても活用の幅が広がります。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
土地の資産性を高めるポイント

4-1. 都市部と郊外の価値の違い
土地の価値は「立地」に大きく依存します。特に都市部の駅近や商業施設が集積するエリアは、需要が安定しており、資産価値が落ちにくい傾向があります。一方、郊外は都市部と比べて購入価格が抑えられるため広い土地を確保しやすいというメリットがあるものの、人口減少や利便性の低さから将来的に価値が下がるリスクも抱えています。
ただし、必ずしも都市部だけが有利というわけではなく、郊外でも高速道路や鉄道の新設、ショッピングモールの開業などにより資産性が高まる場合があります。購入時には「現在の価値」だけでなく「将来の発展可能性」に注目することが重要です。
4-2. 再開発エリア・人気学区の資産性
近年注目されているのが、再開発エリアや人気学区周辺の土地です。再開発が進む地域は新たな商業施設や公共交通の整備が行われ、街全体の利便性が高まります。その結果、不動産価格が上昇するケースが多く、早い段階で購入すれば将来的に高い資産価値を得やすくなります。
また、小中学校や高校の教育環境が整った「人気学区」も資産性を左右する大きなポイントです。子育て世代からの需要が安定するため、住宅需要が減りにくく、長期的に価値を維持しやすいのが特徴です。20代~30代で購入を考える場合、将来の子育てや資産性の両面を満たす立地選びが大切です。
4-3. 将来の売却を見据えた土地選び
住宅購入は一生住み続ける前提で検討されがちですが、転勤やライフスタイルの変化により売却や賃貸に出す可能性も十分にあります。その際に「売りやすい土地」かどうかが資産性を大きく左右します。駅や主要道路から近い、生活インフラが整っている、災害リスクが低いといった条件を備えた土地は、将来的に需要が安定しやすくなります。
逆に、利便性が低い場所や需要が限定的な土地では売却が難しく、価格も下がりやすい傾向があります。
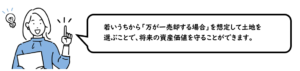
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
建物の資産性を維持する方法

5-1. 建物のメンテナンスと価値維持
建物の資産価値は、築年数の経過とともに下落するのが一般的です。しかし、適切なメンテナンスを行うことで、下落スピードを緩やかにし、長期的に価値を保つことが可能です。外壁塗装や屋根の補修、給排水設備の交換など、定期的な点検と修繕を行うことで建物の寿命を延ばすことができます。特に20代~30代で住宅を購入する場合、数十年にわたって住み続けることを前提に、計画的にメンテナンス費用を積み立てておくことが重要です。
5-2. リフォーム・リノベーションによる資産価値向上
中古市場では、築年数が経った建物でもリフォームやリノベーションが行われている物件は高い評価を受けやすい傾向にあります。最新の設備やデザインに更新することで居住性が向上するだけでなく、売却時の競争力も高まります。例えば、オープンキッチンやワークスペースの設置など、ライフスタイルの変化に合わせた改修は将来の需要に直結します。
また、省エネ設備や断熱性能の改善など、環境性能を高めるリノベーションは、長期的に住宅コストを下げつつ資産価値を高める効果もあります。購入後も資産性を意識したリフォーム計画を立てることで、将来の資産形成に役立ちます。
5-3. 耐震性・省エネ性能と将来価値
近年の住宅市場では、建物の性能が資産価値を大きく左右しています。特に注目されているのが耐震性と省エネ性能です。耐震基準を満たす住宅は災害リスクが低く、購入希望者に安心感を与えます。一方、省エネ性能が高い住宅は光熱費を抑えられるだけでなく、環境意識の高まりから需要が高まっています。
国や自治体が推進する「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)」や「長期優良住宅」といった制度を活用すれば、資産価値を維持しやすくなるだけでなく、補助金や税制優遇を受けられるメリットもあります。性能を意識した住宅づくりは、長期的にみて大きな資産価値の差につながります。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
資産としての住宅とライフプラン
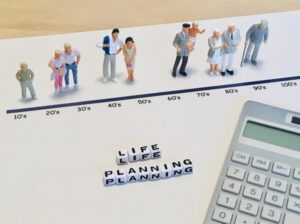
6-1. 家族の成長と資産価値の変化
住宅は単なる「住まい」ではなく、ライフプランと密接に結びついた資産です。20代~30代で購入した場合、子育てや家族構成の変化に応じて住宅の使い方や資産価値の感じ方も変わってきます。例えば、子どもが小さい時期には広いリビングや安全な環境が重視されますが、成長して独立すると広さが過剰になり、将来的に売却や賃貸を検討するケースも出てきます。
こうした変化を前提に、家族構成に合わせて資産価値を最大限に活かせる住宅を選ぶことが大切です。
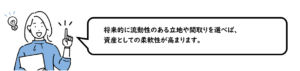
6-2. 転勤・転職を見据えた住宅戦略
近年は働き方の多様化により、転勤や転職の可能性が高まっています。購入した住宅が資産として強みを持っていれば、転居が必要になった場合でも売却や賃貸として活用することができます。特に駅近や利便性の高いエリアの物件は、需要が安定しているため市場に出した際に流動性が高いのが特徴です。
逆に流動性が低い土地を選ぶと、転居時に売却が難しく資産としての魅力が損なわれるリスクがあります。20代~30代での購入時には「自分が住む」視点だけでなく「他者に貸す・売る」視点を持つことが資産戦略として欠かせません。
6-3. 教育費・老後資金とのバランス
住宅購入はライフプランにおける大きな支出の一つですが、同時に教育費や老後資金とのバランスを考えることが重要です。特に子どもの教育費は20代~30代の購入後から数年で増加していくため、無理のないローン計画を立てる必要があります。
また、住宅ローンを完済した後には老後資金が必要となりますが、資産としての住宅がしっかりと価値を維持していれば、売却や住み替えで資金を確保することも可能です。
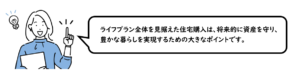
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
住宅購入と地域の価値

7-1. インフラ整備と資産価値の関係
住宅の資産価値は、地域のインフラ整備と深く関わっています。道路の拡張や新しい鉄道路線の開通、大型商業施設や医療機関の建設などは、その地域全体の利便性を高め、不動産需要を押し上げます。例えば、将来的に新駅ができるエリアや再開発が予定されている地域では、土地価格が上昇するケースが多く見られます。20代~30代で住宅を購入する際には、現在の利便性だけでなく、都市計画や再開発計画を確認し「将来的に価値が上がる可能性のある地域」を選ぶことが資産形成の鍵となります。
7-2. 地域コミュニティが持つ資産性
資産価値は利便性だけでなく、地域コミュニティの質によっても左右されます。治安の良さや地域のつながり、子育て支援や住民活動の活発さなどは、外から見えにくいものの、その地域の「住みやすさ」を大きく左右します。住みやすい地域は自然と人気が集まり、需要が安定するため、資産価値が下がりにくい傾向があります。特に子育て世代の20代~30代にとっては、教育や安全性といった観点が住宅選びの重要な基準となり、資産価値にも直結します。
7-3. 自然災害リスクと住宅価値
地域を選ぶ際に見逃せないのが、自然災害リスクです。日本は地震や台風、水害のリスクが高い国であり、災害リスクのあるエリアでは将来的に資産価値が下がる可能性があります。洪水ハザードマップや地盤調査の情報を確認することで、災害リスクを回避した土地選びが可能になります。また、災害に強いエリアや高台に位置する土地は需要が安定しやすく、資産価値の下落リスクも抑えられます。住宅を資産として考える上で、安全性は将来の価値を守るための大きな要素なのです。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
不動産市場の変動と住宅資産

8-1. 景気や金利変動と住宅価値
住宅資産の価値は、経済全体の景気動向や金利の変動に影響を受けます。景気が好調で所得が増えると住宅需要が高まり、価格が上昇しやすくなります。

8-2. 中古住宅市場活用
近年、中古住宅市場が拡大しており、資産性を意識した購入戦略が可能になっています。立地が良く、建物の状態が良好であれば、中古物件でも資産価値は維持できます。また、リノベーションを前提に購入することで、購入価格を抑えつつ資産価値を高めることができます。市場の流動性を活用することで、将来の売却や賃貸に柔軟に対応できます。
8-3. 市場動向を読む力と資産戦略
住宅を資産として考えるには、市場動向を読む力も必要です。不動産価格の上昇・下落のタイミングを把握することで、購入や売却の最適なタイミングを見極めることができます。また、地域ごとの人口動態や開発計画、インフレや金利の動向を理解することで、住宅資産の価値を長期的に守る戦略を立てやすくなります。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
住宅を「負債」にしないための考え方

9-1. 無理のないローン計画
住宅を資産として活かすためには、無理のないローン計画が不可欠です。返済額が家計を圧迫すると、生活の質が低下し、住宅が負債化してしまいます。収入やライフプランを踏まえ、将来の教育費や老後資金を考慮した返済計画を立てることが重要です。20代~30代の購入であれば、長期ローンを活用して毎月の返済負担を抑えることが可能です。
9-2. 維持管理費の計画
住宅は購入後も固定資産税や修繕費、保険料などの費用がかかります。これらの費用を計画的に準備しておくことで、資産価値を維持しつつ住宅を負債化させないことができます。購入時に将来のメンテナンス費用を見積もることも、資産形成の一環です。
9-3. 資産価値を意識した選択
立地や建物の性能、将来的な需要を意識して住宅を選ぶことで、資産価値を守ることができます。「住みやすさ」だけでなく「売りやすさ」「貸しやすさ」を考慮することで、住宅が負債になるリスクを減らせます。購入時に資産価値を意識することが、長期的な資産形成の鍵となります。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
20代~30代が今からできる住宅資産戦略

10-1. 長期的視点での立地選び
若いうちに住宅購入を検討する場合、将来の価値を見据えた立地選びが重要です。駅近や人気学区、将来的に開発が見込まれるエリアなど、資産価値が安定または上昇しやすい地域を選ぶことで、長期的な資産形成につながります。
10-2. 住宅ローンと貯蓄のバランス
住宅ローン返済と並行して、教育費や老後資金の積み立ても行うことで、将来の資産形成を加速できます。ローンは無理なく返済できる範囲で組み、余裕資金を貯蓄や投資に回すことで、住宅と他の資産をバランスよく育てる戦略が有効です。
10-3. 定期的な資産評価と見直し
住宅は購入後も資産価値を維持するため、定期的な資産評価や市場動向の確認が必要です。建物のメンテナンス、リノベーション、地域開発情報の収集を行い、必要に応じて売却や賃貸を検討することで、住宅資産を最大限に活かすことができます。
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
まとめと今後のステップ
1.理想の住まいを実現するために
まずは、おうちの買い方相談室にご相談下さい!
おうちの買い方相談室では、地元の住宅会社を無料で紹介しています。
お客様一人ひとりに合った工務店やハウスメーカーを提案しているため、お気軽にご覧ください!
<おうちの買い方相談室 高崎店 個別相談申込(オンライン相談も可)>
群馬県で注文住宅を建てる際には、予算、土地選び、設計、ハウスメーカー選びなど、いくつもの要素を慎重に考慮する必要があります。
忙しい中、なかなかすべてを考慮し、家づくりを進めるのはとても大変です。
是非、プロを味方につけて、自分たちのライフスタイルや将来設計を踏まえて、最適な選択を行い、理想の住まいを実現してください。
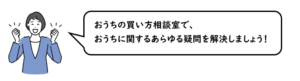
おうちの買い方相談室では、地元の住宅会社を無料で紹介しています。
お客様一人ひとりに合った工務店やハウスメーカーを提案しているため、お気軽にご相談ください!

